ノルウェーの現地メディアは8月14日、アメリカのトランプ大統領がノーベル平和賞の受賞を望んでいることを先月、ノルウェーの財務相に伝えたと、報じました。
ノルウェーの経済紙「ダーゲンズ・ナーリングスリーブ」によりますと、アメリカのトランプ大統領は先月、ノルウェーのストルテンベルグ財務相と電話で話した際に、ノーベル平和賞の受賞を望んでいることを伝えたということです。
実はノーベル平和賞の要求は今回が初めてではなかった!

実はトランプ大統領がノーベル平和賞を要求したのは今回が初めてではありません。
ノルウェーの財務相を長年務めたシーブ・イェンセン氏が著書で暴露をしています。
トランプ氏は彼女に対し、自身がノーベル平和賞を受賞できるよう、選考委員会に働きかけてほしいと直接要求したといいます。
この暴露は、政治権力者がノーベル賞の権威に介入しようとする、極めて異例な実態を白日の下に晒すものでした。世界は、この前代未聞の「圧力」疑惑に瞬く間に注目しました。
暴露された電話、その生々しいやり取り
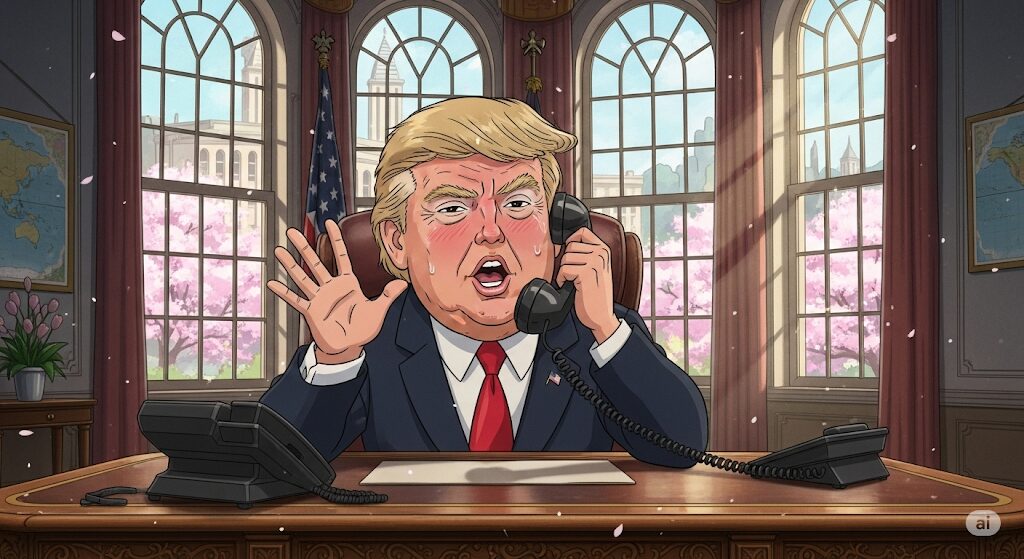
彼女の回顧録によると、電話の初期の議題は貿易問題などであったが、トランプ氏はおもむろに本題を切り出したとされます。
彼は、北朝鮮の金正恩)総書記との歴史的な会談を実現したことを強調し、自身がノーベル平和賞にふさわしいと強く主張したといいます。
そして、イェンセン氏に対し、ノーベル平和賞の選考を行う「ノルウェー・ノーベル委員会」に影響力を行使するよう、直接的に要求しました。
この予期せぬ要求に対し、イェンセン氏は強い衝撃を受けました。彼女は著書の中で、その時の心境を「完全に常軌を逸している」と感じたと綴っています。
政府の閣僚である自身が、独立した組織であるノーベル委員会に介入することはありえず、その要求自体が民主主義国家の常識からかけ離れていたからです。
彼女はこの要求を丁重に、しかしきっぱりと断ったといいます。この生々しいやり取りは、トランプ氏の型破りな、そして時に強引な政治手法を象徴するエピソードとして世界に報じられました。
なぜこれが「越えてはならない一線」なのか

トランプ氏の要求がなぜ「常軌を逸している」とまで言われるのか。その理由は、ノーベル平和賞が守り続けてきた厳格な独立性にあります。
ノーベル平和賞は、アルフレッド・ノーベルの遺言に基づき、スウェーデンではなくノルウェーの国会が選出した5人の委員からなる「ノルウェー・ノーベル委員会」が選考を行います。
委員はノルウェーの元政治家や学者などで構成されますが、一度選出されれば、その決定はノルウェー政府や国会、さらには国王からさえも一切の干渉を受けません。
これは、同賞の権威と公平性を担保するための絶対的な原則です。
この制度上、一国の政府閣僚が委員会に働きかけることは、賞の理念そのものを根底から覆す行為であり、絶対に越えてはならない一線なのです。

トランプ氏がノルウェーの閣僚に直接電話で影響力行使を依頼したことは、この神聖なルールを全く理解していないか、あるいは理解した上で意図的に無視しようとしたことを示唆しています。
これは単なる儀礼上の問題ではありません。もし政治権力が賞の選考に介入できるようになれば、ノーベル平和賞は権力者のための道具に成り下がり、その価値は失墜するでしょう。
イェンセン氏がトランプ氏の要求を異常だと感じたのは、まさにこの民主主義と中立性の根幹が揺るがされかねない危険性を瞬時に察知したからに他なりません。
繰り返されていた「平和賞への執着」

今回のニュースが衝撃的であるのは、これが単発の思いつきではなく、トランプ氏のノーベル平和賞への根強い執着の一端を示すものだったからです。事実、彼の同様の行動は複数の証言によって裏付けられています。
最も有名なのが、日本の安倍晋三元首相に対する推薦依頼です。トランプ氏は2019年、記者団に対し、安倍氏から「最も美しい5ページの手紙」を受け取り、ノーベル平和賞に推薦されたと自ら明かしました。

後の報道によれば、これは米朝首脳会談後、米政府側から日本側へ非公式に打診があったものとされています。国家のトップが他国のトップに賞の推薦を依頼するというのも、極めて異例のことです。
さらに、トランプ政権で大統領補佐官(国家安全保障担当)を務めたジョン・ボルトン氏も、自身の回顧録『それが起きた部屋』の中で、トランプ氏がノーベル平和賞に異常なこだわりを持っていたと証言しています。
ボルトン氏によれば、トランプ氏はバラク・オバマ前大統領が受賞したことに強い対抗意識を燃やしており、「オバマにできて、なぜ俺にできないんだ」という意識が、北朝鮮や中東での外交政策の動機の一つにすらなっていた可能性があると指摘しています。
これらの証言は、今回のニュースや、イェンセン氏の暴露と見事に符合します。複数のルートで、自身の政治的功績を「ノーベル平和賞」という最高の権威によって認めさせようと試みていた、トランプ氏の人物像と行動原理が浮かび上がってきます。
今回のニュースが意味するもの

今回のニュースは単なる一国の元首のゴシップにとどまりません。この一件は、ドナルド・トランプという政治家のスタイルを象徴しています。
それは、目的のためには既存のルール、慣例、そして時には民主主義の根幹にある原則さえも軽視しかねないという危うさです。
彼にとって、独立した機関の権威や、国家間の儀礼的なプロトコルは、自身の目的を達成するための「交渉可能な」対象に過ぎなかったのかもしれません。
これはあくまで推測の域を出ませんが、彼のビジネスマンとしての経歴を考えれば、そうした発想に至った可能性は否定できません。
このスタイルは彼の支持者からは「既成概念を打ち破るリーダーシップ」と映る一方で、批判的な層からは「規範を破壊する危険な兆候」と見なされます。



コメント