「夏休みの宿題、自由研究だけが残ってる…」
「何から手をつけていいか分からない!」
夏休みも終盤になると、多くの小学生と保護者の方を悩ませるのが自由研究です。でも、ご安心ください。今からでも間に合う、たった2時間程度でできる面白い自由研究はたくさんあります。
話題のワダイでは、学年別に具体的なテーマと進め方、まとめ方のコツまでを分かりやすくご紹介します。準備も簡単なものばかりなので、すぐに取り組めますよ。
【低学年向け】2時間でできる自由研究テーマ 3選
まずは、実験そのものが楽しめる低学年向けのテーマです。親子で一緒にワイワイ楽しむのが成功のコツです!
ふわふわスライム作り!色と感触を楽しもう
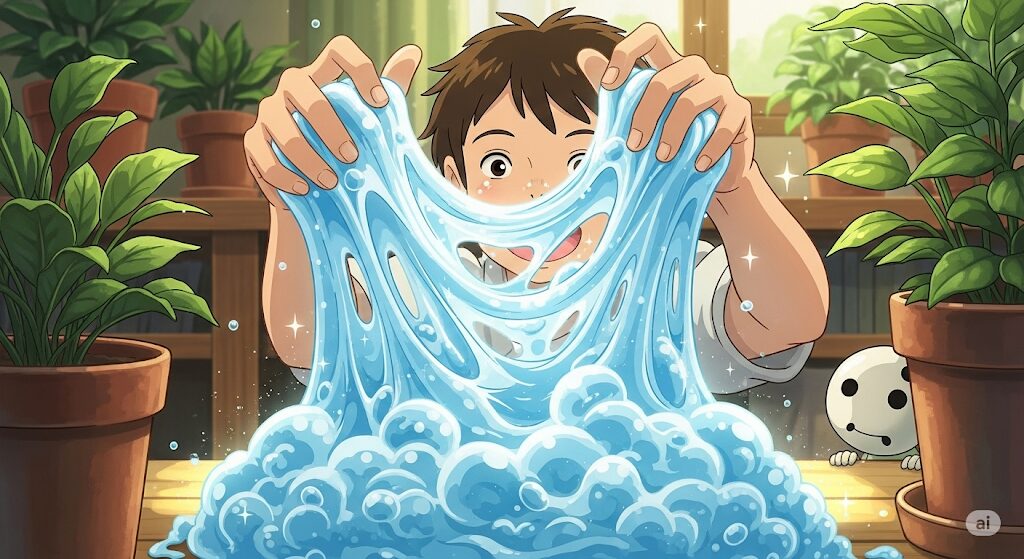
身近な材料で、不思議な感触のスライムを作る大人気の実験です。絵の具を混ぜて好きな色にしたり、ラメやビーズを入れたりして、自分だけのオリジナルスライム作りを楽しめます。
準備するもの
- 洗濯のり(PVA配合のもの)
- ホウ砂(薬局で手に入ります)目薬やコンタクト洗浄液でもOK
- 水
- 絵の具
- 紙コップ、割りばし
- (お好みで)ラメやビーズ
進め方
- 紙コップに水とホウ砂を少し入れてよく混ぜ、ホウ砂水を作ります。
- 別の紙コップに洗濯のりと水を入れ、好きな色の絵の具を混ぜます。
- 色を付けたのりの方に、ホウ砂水を少しずつ加えながら割りばしでよーく混ぜます。
- 固まってきたら、手でこねて感触を楽しみましょう。
まとめ方
作ったスライムの写真を撮ったり、絵に描いたりして画用紙に貼りましょう。
「あかとあおをまぜたらむらさきになったよ」
「ビーズをいれたらつぶつぶでおもしろかった」
など、発見したことや感想を素直な言葉で書くのがポイントです。
野菜の浮き沈み実験!お料理前にお手伝い研究

水に入れると浮く野菜と沈む野菜があるのはなぜでしょう?色々な野菜で試してみる実験です。お家の人のお料理のお手伝いにもなって一石二鳥!
準備するもの
- 大きなボウルや鍋(透明だと見やすい)
- 水
- いろいろな野菜(きゅうり、トマト、にんじん、ピーマン、じゃがいも、かぼちゃなど)
- (あれば)はかり
進め方
- ボウルに水をたっぷり入れます。
- それぞれの野菜が「浮く」か「沈む」か、先に予想してみましょう。
- 野菜を一つずつ水の中へそっと入れて、どうなるか観察します。
まとめ方
「うくやさい」「しずむやさい」の表を作って、結果をシールや丸印で記録します。野菜の絵を描いて、水に浮いている様子や沈んでいる様子を表現するのも良いでしょう。
「おもいきゅうりがういて、かるいミニトマトがしずんでびっくりした」など、予想と結果がどう違ったかを書くと、立派な考察になります。
シャボン玉を割れにくくするには?最強シャボン液作り

どうやったら割れにくいシャボン玉が作れるか、シャボン液に色々なものを混ぜて最強のシャボン液作りを目指す実験です。
準備するもの
- 食器用洗剤
- 水
- 砂糖
- 洗濯のり
- ガムシロップ
- ストロー、うちわの骨など
- 計量カップ、コップ
進め方
- 「水+洗剤」だけの基本のシャボン液を作ります。
- 基本のシャボン液に、砂糖、洗濯のり、ガムシロップをそれぞれ別のコップで混ぜて、4種類のシャボン液を用意します。
- どのシャボン液が一番大きくて割れにくいシャボン玉を作れるか、外で飛ばして比べてみましょう。
まとめ方
4種類のシャボン液の結果を比べた表を作りましょう。「おおきさ」「われにくさ」などで点数をつけても面白いです。
「さとうをいれたら、すこしわれにくくなったよ」
というように、何を入れたらどう変わったかを具体的に書くことが大切です。
【高学年向け】2時間でできる自由研究テーマ 3選
高学年向けには、結果の背景にある「なぜ?」を探求する、少し本格的なテーマをご紹介します。
氷がとける時間を競争させよう!

氷に塩をかけると早く溶けるのは有名ですが、他のものでも変化はあるのでしょうか?身近な粉末調味料を使って、氷が溶ける速さを比較する科学実験です。
準備するもの
- 同じ大きさの氷(製氷皿で作る)
- お皿(4〜5枚)
- 塩、砂糖、片栗粉、小麦粉など、家にある粉末
- ストップウォッチ
- (あれば)温度計
進め方
- お皿に氷を一つずつ乗せます。一つは何もかけない比較用の氷にします。
- それぞれのお皿の氷に、同じ量(例:小さじ1杯)の粉末をふりかけます。
- 予想: どれが一番早く溶けるか、理由と共に予想を立てます。「塩が一番早いはず。砂糖はどうだろう?」
- ストップウォッチで時間を計り、完全に溶けきるまでの時間を記録します。5分おきに様子を写真に撮るのもおすすめです。
まとめ方
- 動機・予想: なぜこの実験をしようと思ったかと、実験前の予想を記述します。
- 方法: 実験の手順を詳しく書きます。
- 結果: 溶けるまでにかかった時間をグラフ(棒グラフなど)にすると、結果がひと目で分かります。
- 考察: なぜ塩をかけると早く溶けるのか(凝固点降下)、砂糖や他の粉ではどうだったのかを調べ、結果と結びつけて考えます。「塩には氷の溶ける温度を下げる働きがあることが分かった」など、調べたことと自分の結果から分かったことを書きましょう。
スポーツドリンクは本当に体に吸収されやすいのか?

「体に素早く吸収される」と言われるスポーツドリンク。本当に水より吸収されやすいのか、植物を使って可視化(見える化)する実験です。
準備するもの
- 切り花(白や薄い色のカーネーション、菊などがおすすめ)
- スポーツドリンク(色のついたもの)
- 水
- 食紅(赤や青)
- 同じ形のコップや瓶(2つ)
進め方
- 一つのコップにスポーツドリンクを、もう一つのコップには食紅で色を付けた水を同じ量入れます。
- 切り花の茎をカッターで少し切ってもらい(※お家の人に手伝ってもらう)、すぐにそれぞれのコップにさします。
- 予想: どちらの花が早く色づくか予想します。「スポーツドリンクの方が、吸収が速いから早く色づくはずだ」
- 30分後、1時間後、2時間後…と、花びらの色の変化を観察・記録します。
まとめ方
- 動機・予想: スポーツドリンクのうたい文句に疑問を持ったことなどを書きます。
- 方法: 写真を交えて、手順を分かりやすく説明します。
- 結果: 時間ごとの花びらの染まり具合を写真やスケッチで記録し、比較します。
- 考察: 結果から何が言えるかを考えます。「植物の水の吸い上げる力(毛細管現象)で茎が染まった。今回の実験では、水とスポーツドリンクで大きな差は見られなかった」など、分かったことや、そこから生まれた新たな疑問を書くと、より深い研究になります。
果物電池でLEDは光るか?

レモンやミカンなどの果物が電池になるって本当?身近な果物を使って電気を起こし、LED豆電球を光らせることに挑戦する実験です。
準備するもの
- レモン、みかん、キウイ、じゃがいもなど(水分が多いものが良い)
- 銅板、亜鉛板(ホームセンターなどで購入可能)
- みのむしクリップ付き導線(2〜3本)
- LED豆電球(低電圧で光るもの)ホームセンターで売っています。
- (あれば)電子メロディ、テスター(電圧計)
進め方
- 果物を少し揉んで柔らかくします。
- 果物に、銅板と亜鉛板を少し離して差し込みます。これが「+極」と「−極」になります。
- みのむしクリップで、銅板とLEDの長い足、亜鉛板とLEDの短い足をそれぞれ繋ぎます。
- 挑戦: 光が弱かったり光らなかったりした場合、果物を2つ、3つと「直列つなぎ」にしてみましょう。(果物Aの亜鉛板と果物Bの銅板を導線でつなぐ)
まとめ方
- 動機: なぜ果物で電気が起きるのか不思議に思ったことなどを書きます。
- 方法: 電池の仕組みの図や、実験装置の写真を載せて説明します。
- 結果: どの果物でLEDが光ったか、光の強さはどうだったかを記録します。テスターがあれば、測定した電圧を記録するとより本格的になります。
- 考察: なぜ果物で電気が起きるのか(イオン化傾向の違いなど)を調べ、まとめます。「果物の水分に含まれる酸が電解質の役割をし、2種類の金属(銅と亜鉛)の間で電子が移動することで電気が発生することが分かった」など、科学的な仕組みに踏み込んでみましょう。
まだまだある!短時間でできる自由研究アイデア
今回紹介したテーマの他にも、お家で簡単にできる研究はたくさんあります。いくつか例をご紹介しますね。
| テーマ | こんなことがわかる・できる |
|---|---|
| 10円玉ピカピカ実験 | 酸性の液体(お酢、レモン汁など)が金属のサビ(酸化)をきれいにする仕組みがわかる。 |
| アリの行列観察 | アリがどんなものを好んで運び、どうやって仲間とコミュニケーションをとっているのか観察できる。 |
| いろいろな紙の吸水力くらべ | キッチンペーパーや新聞紙、画用紙などがどれだけ水を吸うか、その違いを調べられる。 |
| 太陽で動く時計(日時計)作り | 太陽の動きと時間の関係を学びながら、自分だけの日時計を作ることができる。 |
| 氷に糸がくっつく?不思議な実験 | 「再氷結」という現象を利用して、氷に糸をくっつけて持ち上げるマジックのような実験ができる。 |
| 野菜の切り口を観察しよう | いろいろな野菜の断面をスタンプにしたり、スケッチしたりして、植物のつくりを観察できる。 |
| ペットボトルでろ過装置作り | 汚れた水が砂や小石、炭などを通ることで、きれいになっていく仕組みを体験できる。 |
| いろいろなものの燃え方観察 | ろうそくの炎を観察したり、燃えやすいもの・燃えにくいものを比較したりできる(※必ず大人の人と一緒に!) |
まとめ
今回は、短時間でできる自由研究のテーマを低学年向け・高学年向けに分けてご紹介しました。スライム作りのような楽しい実験から、科学の不思議に迫る本格的な研究まで、たくさんのアイデアがありましたね。
自由研究で一番大切なのは「これ、なんだろう?」「どうしてこうなるの?」という、自分の「知りたい!」という気持ちです。今回ご紹介したテーマの中に、あなたの好奇心をくすぐるものがあれば嬉しいです。
ぜひ、この夏は自由研究を楽しみながら、新しい発見をしてみてください!



コメント