参議院選挙の結果や、野党・国民民主党からの強い要求を受け、政府・与党内でガソリン税の一部を軽減する案の議論が本格化しています。
しかし、その裏で減税によって失われる財源を補うため、新たな税制度「走行距離課税」の導入が検討されるようです。
この新しい税金は一体どのようなもので、私たちの生活にどんな影響を与えるのでしょうか。
話題のワダイでは、賛成・反対、それぞれの立場から詳しく見ていきます。
新たな候補「走行距離課税」とは?

走行距離課税とは、その名の通り自動車の走行距離に応じて課税する仕組みです。
現在、道路の維持管理費などは、主にガソリンに上乗せされる「ガソリン税」によって賄われています。
しかし、電気自動車(EV)や燃費の良いハイブリッド車の普及により、ガソリンを消費しない、あるいは消費量が少ない車が増え、税負担の不公平が生じています。
走行距離課税は、この不公平感をなくし、「道路を利用した分だけ公平に負担する」という考え方(受益者負担の原則)に基づいた制度として注目されています。
賛成の声 👍 「公平な負担」と「安定財源」への期待

走行距離課税に賛成する人々は、主に税の公平性と安定した財源の確保を重視しています。
✅ 公平性の実現
「乗る人ほど負担すべき」という考え方です。EVであっても道路を使う以上、その維持費を負担するのは当然であり、走行距離で課税するのが最も公平だと主張します。
✅ 「乗らない人」の負担軽減
車を所有していても、運転する機会が少ない人にとっては、現在の所有ベースの税金よりも負担が軽くなる可能性があります。
✅ 安定した道路財源の確保
今後、EVへの移行が進みガソリン税収が減少しても、道路の維持管理に必要な財源を安定して確保できると期待されています。
✅ 環境への配慮
走行距離に応じて課税されることで、無駄な車の利用を控えるインセンティブが働き、CO2排出量の削減に繋がるという意見もあります。
反対の声 👎 「地方いじめ」「二重課税」への強い懸念

反対意見は非常に根強く、特に地方在住者や事業者からは生活や経済を脅かすものとして強い反発が生まれています。
✅地方在住者の生活を直撃
公共交通機関が未発達で、車が生活必需品である地方住民にとっては、走行距離が長くなるため、税負担が生活を直接圧迫します。「地方いじめだ」という悲痛な声も上がっています。
✅物流・運送業界への大打撃
長距離輸送を担う運送業界にとっては、コスト増が経営に深刻な影響を与えかねません。このコストは最終的に物価上昇という形で、国民全体に跳ね返る恐れがあります。
✅EV普及へのブレーキ
日本自動車工業会(自工会)は、「政府が推進するカーボンニュートラルの方針と矛盾する」として断固反対を表明。EVの維持費の安さというメリットが失われ、普及の妨げになると懸念しています。
✅ガソリン車への「二重課税」
ガソリン車のドライバーからは、現在のガソリン税に加えて新たな税金が課される「二重課税」になるのではないかという強い不満が出ています。
✅プライバシーの問題
個人の走行データを国が把握することになるため、プライバシー侵害への懸念も指摘されています。
まとめ:今後の見通しは?
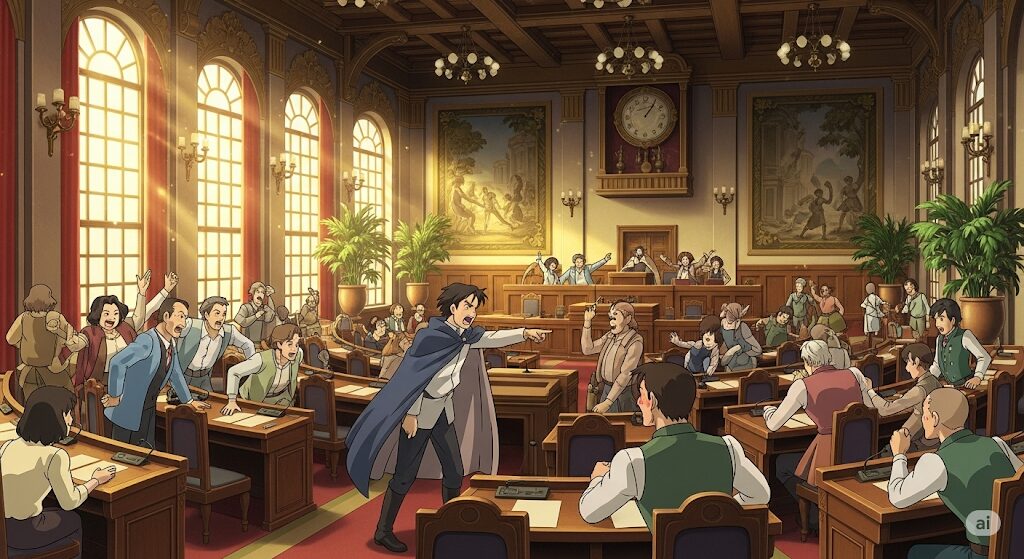
走行距離課税は、税の公平性を確保するための有力な選択肢とされる一方で、多くの国民の生活や日本経済全体に大きな影響を与えかねない、非常にデリケートな問題です。
特に地方や事業者からの強い反発、プライバシーの問題、そしてEV普及との兼ね合いなど、解決すべき課題は山積しています。そのため、具体的な導入時期などは全く決まっておらず、今後も慎重な議論が求められる状況です。



コメント