コメの価格高騰が続く中、江藤農林水産大臣は3月半ばにも政府の備蓄米21万トンを市場に放出する方針を正式に発表しました。
これで令和の米騒動が落ち着けばいいのですが、どうなるでしょうか?
今回放出することになった備蓄米ですが、いったいどこにあるのでしょうか?またなぜ備蓄をしているのでしょうか?
この機会に少し調べてみました。
政府の備蓄米のしくみ
日本政府の備蓄米制度は、1995年に「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」の施行により発足しました。
備蓄米は、農林水産省が管理し、全国各地の指定倉庫に保管されています。具体的な保管場所の詳細は公表されていませんが、以下のような場所に分散されて保管されているようです。
備蓄米の保管場所
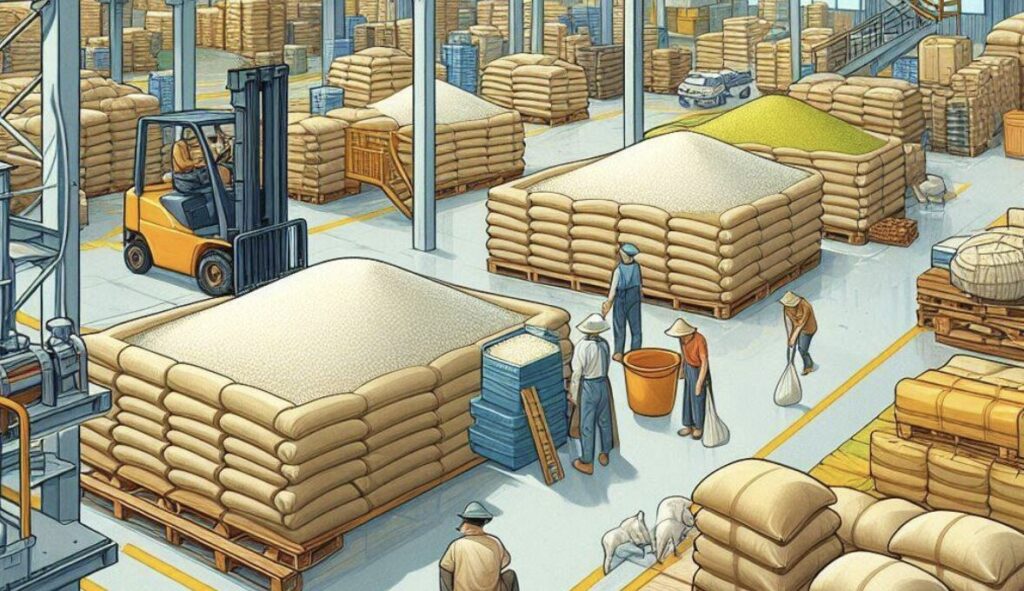
- 全国の民間倉庫
政府が全国各地の民間の穀物倉庫を借りて備蓄米を保管しています。これにより、災害時や食糧不足時に迅速に供給可能となっています。 - JA(農業協同組合)などの施設
一部の農協や関連施設も保管場所として活用されているようです。 - 港湾・物流拠点に近い倉庫
緊急時に日本各地に素早く配送できるよう、大規模な港の近くにも配置されています。
備蓄米が分散して保管される理由
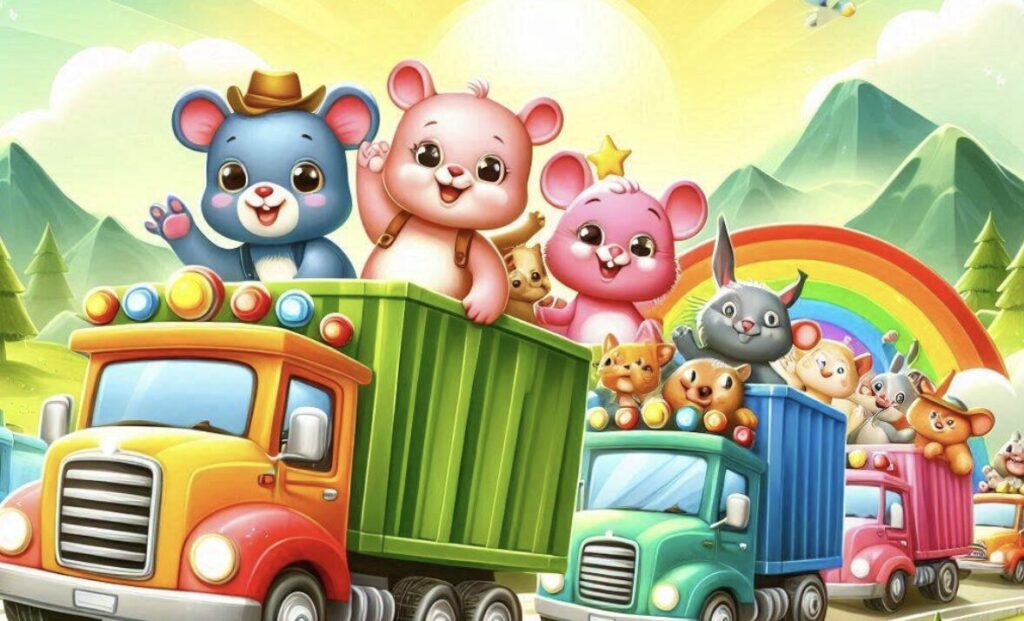
備蓄米を一か所で保管すると、災害時にすべての備蓄米が影響を受けるリスクがあるため分散して保管されています。
また、複数箇所で保管することで、ある地域で災害が発生して備蓄米が必要になったときに、近くの保管場所からより迅速に輸送ができるというメリットもあります。
備蓄米の保管はどのようにされているのか

備蓄米は、温度と湿度が厳格に管理された低温倉庫で保管されます。一般的に、以下の条件が守られています。
- 保管温度
15℃以下に維持することで米の劣化を防ぐ。 - 湿度管理
60~65%の適切な湿度を保ち、乾燥やカビの発生を防止。 - 害虫・カビ対策
定期的な点検を実施し、必要に応じて防虫処理を行う。
これらの条件を維持することで、長期間にわたって高品質の米を保管することができます。
備蓄米はどのような時に放出されるのか

備蓄米は年間約100万トンを維持するようになっています。この量は日本の年間米需要量の約8分の1に当たります。
保管期間は5年間で、期間を過ぎた備蓄米は、学校給食、福祉施設、加工用米、飼料用として販売・提供されています。
また、大規模災害時には自治体を通じて無償提供されることもあります。
今回は上記の運用方針に追加して、流通に支障が生じた場合にも市場に放出できるよう規則を緩和することになりました。
まとめ

政府備蓄米は、災害時や市場の価格変動に対応する重要な役割を担っています。全国に分散して保管され、徹底した品質管理のもとで維持されています。
ただ、保管にかかるコストの上昇も問題となっています。
今後は、保存技術の向上や省エネルギー化が求められ、より効率的な備蓄システムの構築が進められるでしょう。また、備蓄米の存在をより多くの人に知ってもらうための広報活動も必要です。
そういった意味では今回の米騒動は国民が備蓄米について知るいい機会だったとも言えます。




コメント