「ああ、紙がない…」 公衆トイレで経験するあの絶望的な状況…あなたは経験したことありますか?。しかし、現代中国の一部の都市では、その悩みの質がちょっと違うようです。
なんと、トイレットペーパーを手に入れるために「広告視聴」や「顔認証」が必須になっているというのです!

経費削減と盗難防止が目的らしいのですが、その斜め上すぎる発想に、もはや笑うしかありません。話題のワダイでは、そんな中国のハイテクすぎる公衆トイレ事情と、それに対するリアルな中国人の反応を、掘り下げてみたいと思います。
選べる2つの試練!「顔認証」or「広告視聴」
さて、あなたが中国の最新式公衆トイレに入ったとしましょう。個室に入る前、まずあなたを待ち受けるのは、トイレットペーパーディスペンサーという名の番人。この番人を突破し、貴重な紙を手に入れる方法は、主に2つ用意されています。
コース1:サイバーパンクな「顔認証」

ディスペンサーの前に立ち、カメラをじっと見つめる…。まるでSF映画のワンシーンですが、これが現実。
- カメラに顔をスキャンさせる。
- 認証成功!ウィーン…と規定量(約60cm)の紙が出てくる。
- おかわりは9分後まで待て!
そう、連打はできません。あなたの顔データと引き換えに、最低限の紙が支給されるシステム。もはや「あなたの顔の価値=トイレットペーパー60cm」と言っても過言ではないでしょう。究極の個人情報ビジネスが、まさかトイレで展開されていたとは…。
コース2:資本主義の洗礼「広告視聴」

「顔を差し出すのはちょっと…」というシャイなあなたには、こちらのコースがおすすめ。
- スマホでディスペンサーのQRコードをスキャン。
- 表示された5秒〜15秒の広告動画を視聴する。
- 視聴完了!おめでとうございます!紙をゲットです!
緊急事態の数秒間、あなたは企業のプロモーションに付き合わなければなりません。まさに「時は金なり」ならぬ「紙は広告なり」。切羽詰まった状況で見せられる広告、果たしてその効果はいかほどなのでしょうか。
なぜこんなことに?背景には「ペーパー大泥棒」

「なんでこんな面倒なことに…」と思いますよね。実は、この奇妙なシステムの裏には、深刻な社会問題が隠されていました。
それは、トイレットペーパーの過剰な持ち去り問題です。
設置されたペーパーをロールごと持ち去ったり、家庭で使うためにありえない量を引き出して持ち帰ったりする人が続出。これではいくら補充しても追いつきません。管理側としては、まさに死活問題。
そこで生まれたのが、「テクノロジーで利用を制限し、ついでに広告収入で経費削減もしちゃおう!」という、涙ぐましい(?)アイデアだったのです。モラルに訴えるのではなく、システムで強制的に解決する。ある 意味では非常に合理的ですが…うーん、なんだか世知辛い!
現地では賛否両論!リアルな「中国人の反応」
この前代未聞のシステム、現地での評判はどうなのでしょうか?調べてみると、意外にも賛否両論、様々な声が上がっていました。
【賛成派】「盗むヤツが悪いんだから仕方ない」
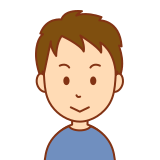
無料で使えるだけありがたい。広告くらい見るよ
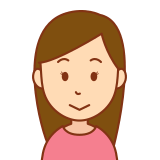
これでトイレが綺麗に保たれるなら良いことよね
タダで提供されるものには対価が必要、という非常に合理的な意見。盗難にウンザリしていた人たちからの支持は厚いようです。
【反対派】「緊急事態だぞ!人間性を疑う!」

お腹が大変な時に広告なんて見てられるか!

スマホがないわれわれ高齢者はどうしたらいいんだ?
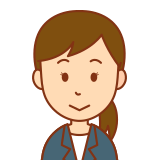
プライバシー(顔情報)がどう使われるか不安すぎるわ
ごもっとも!緊急時に障壁があることへの不満や、デジタル格差問題、そして個人情報への懸念は根強いようです。「そこまでして管理されたくない」という悲鳴が聞こえてきそうですね。
笑い話の先に待つ、ちょっと怖い未来

さて、中国のハイテク公衆トイレ事情、いかがでしたか?
広告視聴や顔認証と引き換えにトイレットペーパーを得る。この話は、遠い国の面白いニュースで終わるでしょうか。
無料サービスには広告がつきまとい、街の至る所に監視カメラがある現代。私たちの日常も、気づかないうちにあらゆるものがデータ化され、何かの対価として差し出されています。

あなたの今日のランチ代は、この広告を30秒見た分で割引です

この公園のベンチに座りたければ、顔認証をどうぞ
なんて未来が、すぐそこまで来ているのかもしれません。
トイレでの数秒間の攻防を笑いながらも、私たちの生活がどこまでテクノロジーとビジネスに踏み込まれていくのか、少しだけ立ち止まって考えてみる良い機会かもしれませんね。



コメント