アメリカ・ワシントン州は、日本の固有種であり「マーダー・ホーネット(殺人スズメバチ)」として恐れられたオオスズメバチの根絶完了を宣言しました。養蜂や農業に深刻な被害をもたらしていただけに、このニュースは大きな注目を集めています。
本来、日本の自然生態系の一部であるオオスズメバチ。しかし、一度海を渡ると、天敵の不在や環境への適応により、現地の生態系を脅かす「侵略的外来種」へと姿を変えてしまいました。
実は、このように日本の生き物が海外で意図せず猛威を振るっている例は、オオスズメバチだけではありません。
話題のワダイでは、アメリカで行われた驚くべきオオスズメバチ根絶作戦の詳細と海外で生態系を乱す侵略的外来種となった日本の固有種ついてご紹介します。
科学と執念の結晶:米国のオオスズメバチ根絶作戦、その詳細に迫る
「マーダー・ホーネット」としてアメリカ国民を恐怖に陥れたオオスズメバチ。ワシントン州農務省(WSDA)が行った根絶作戦は、最新技術と地道な努力、そして市民の協力が一体となった、驚くべきものでした。
ステップ1:敵を見つけ出せ!ハイテクを駆使した巣の特定

広大な森林に潜む巣を特定するため、専門家チームは独創的な手法を用いました。
🐝市民からの情報提供
専用ホットラインやオンライン通報システムを設置し、数千件もの目撃情報を収集。
🐝罠の設置
オオスズメバチが好む液体を入れた罠を多数仕掛け、生きた個体を捕獲。
🐝「追跡装置」の装着
作戦のハイライトです。捕獲したオオスズメバチを氷で冷却して動きを鈍らせ、なんとデンタルフロスを使って超小型の無線発信機を胸部に結びつけました。
🐝追跡
発信機を付けたハチを放し、巣に戻るのをチームが受信機を片手に森の中を走り回って追いかけ、巣の正確な位置を突き止めました。
ステップ2:一匹たりとも逃がすな!徹底的な駆除プロセス

巣の場所が特定されると、まるでSF映画のような特殊部隊が出動しました。
🐝完全防備
メンバーは、強力な毒針を通さない宇宙服のような特殊な防護服を着用。
🐝夜間の奇襲
ハチの活動が鈍る夜間から早朝にかけて作戦を決行。
🐝吸引と密閉
まず、巣がある木の洞に強力な掃除機のホースを差し込み、ハチを次々と吸引。その後、巣がある木の幹全体を巨大な食品用ラップのようなシートで完全に包み込みました。
🐝完全駆除
最後に、密閉されたラップの中に二酸化炭素ガスを注入。巣の中に残っていた全てのハチを窒息させ、一匹残らず完全に駆除することに成功しました。
専門機関、研究者、そして多くの市民からの情報提供という「官民一体」の協力体制で2024年12月18日にワシントン州農業局(WSDA)と米農務省が「オオスズメバチの根絶」宣言しました。
オオスズメバチだけじゃない!海外で猛威をふるう日本の生き物
オオスズメバチ以外にも私たちの身近にいる動植物が、海外では全く異なる顔を見せています。ここではその代表的な例を見ていきましょう。
「南部を飲み込むツル」:クズ(葛)

日本では葛餅や葛根湯の原料として親しまれているクズですが、アメリカでは「南部を飲み込んだツル(The vine that ate the South)」という異名を持つ、最も悪名高い侵略的植物の一つです。
💀侵入の経緯
1876年のフィラデルフィア万国博覧会で日本から紹介されたのが始まりです。当初は庭園植物や土壌流出防止のために政府によって推奨されました。
💀現状と被害
旺盛すぎる繁殖力でアメリカ南東部の広大な土地を覆い尽くしています。1日に30cmも伸びるツルで森林や電柱、家屋まで覆い、光合成を妨げて他の植物を枯死させる「緑の怪物」と化しています。生態系だけでなく、林業やインフラにも甚大な被害を与えています。
建物を破壊する植物:イタドリ(虎杖)

山菜として食べられるイタドリは、ヨーロッパ、特にイギリスで「ジャパニーズ・ノットウィード(Japanese Knotweed)」として知られ、家屋やインフラに深刻なダメージを与えることで恐れられています。
💀侵入の経緯
19世紀に、著名な植物学者シーボルトによって観賞用植物としてヨーロッパに持ち込まれました。
💀現状と被害
イタドリの強靭な根はコンクリートやアスファルトを突き破って成長します。建物の基礎や壁、道路、水道管を破壊するため、イギリスでは敷地にイタドリが生えているだけで住宅ローンが組めなくなるほどの社会問題に。駆除は極めて困難で、天敵である「イタドリマダラキジラミ」を日本から輸入する生物的防除も試みられています。
農作物を食い荒らす害虫:マメコガネ

日本ではごく普通に見られるマメコガネは、北米では「ジャパニーズ・ビートル(Japanese Beetle)」と呼ばれ、農業や園芸における最重要害虫の一つです。
💀侵入の経緯
1916年、ニュージャージー州で発見。苗木と共に輸入された土に幼虫が紛れ込んでいたと考えられています。
💀現状と被害
天敵がいない北米で大発生。成虫は約300種類もの植物の葉や花、果実を食害し、幼虫は芝生の根を食べて枯らしてしまいます。その被害額は年間数億ドルに上るとも言われ、根絶には至っていません。
海の生態系を覆う「海の雑草」:ワカメ
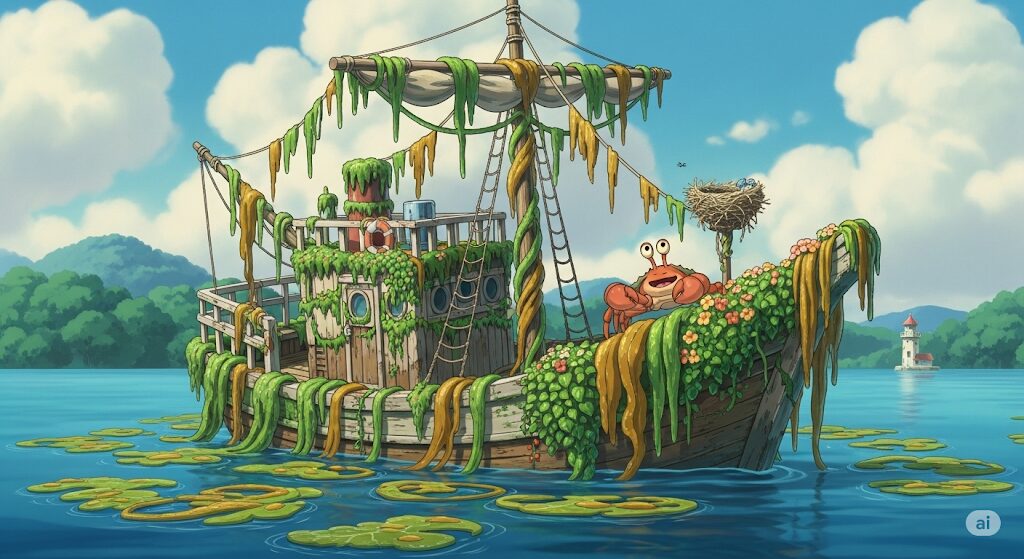
日本の食卓に欠かせないワカメも、IUCN(国際自然保護連合)が定める「世界の侵略的外来種ワースト100」に選定されています。
💀侵入の経緯
大型船舶が船体のバランスを保つために取り込む「バラスト水」に胞子が紛れ込み、世界中の海に拡散しました。
💀現状と被害
ヨーロッパ、オーストラリア、アメリカなど世界各地の沿岸で定着。非常に強い繁殖力で海底を覆い尽くし、現地の海藻類を駆逐。本来の生物の住処や産卵場所を奪い、海の生態系を大きく変えてしまいます。ワカメを食べる習慣のない地域では、増えすぎたワカメは「海の雑草」として漁業などに影響を与えています。
まとめ:グローバル化がもたらす生態系の課題

今回紹介したクズ、イタドリ、マメコガネ、ワカメ、そしてオオスズメバチ。これらの事例は、ある環境では生態系の一部として調和している生物が、ひとたび異なる環境に持ち込まれると、生態系のバランスを崩し、予測不能な影響を与える可能性があることを示しています。
グローバル化が進む現代において、外来種問題は、単なる生態系の保全だけでなく、私たちの経済や社会にも関わる重要な課題となっているのです。



コメント